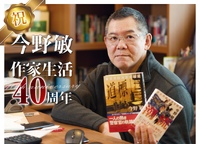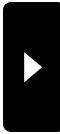2015年04月13日
沖縄空手の歴史
①琉球武術+各国の武術=空手
以前より琉球(沖縄)には「手(ティ)」と呼ばれる武術がありました。
1429年に琉球(沖縄)が尚巴志(しょうはし)により統一され武器を禁じられると
素手の武術である手(ティ)や、農機具等を使った武術が発展します。
その後琉球は、ジャワ・スマトラ・タイや中国等の南国諸国との交流が盛んになり、
同時に各国の武術の要素を吸収、改革され「手」が発展していきます。

②発展した「手」は3つに分かれる
「手」が発展すると、琉球各地に広がりそれぞれの地名をとって
首里手(しゅりて) 那覇手(なはて) 泊手(とまりて)
と呼ばれ始め、それぞれ特徴を持ち始めます。
首里手:関節・スピード(素早さ)を重視 自然な呼吸法
那覇手:筋肉・パワー重視 意識した呼吸法
泊手 :首里手に非常に近いがさらに関節躍動を使った技が多い

③「沖縄4大流派」が起きる
3つの「手」の中心人物や、その弟子たちがやがて様々な流派を興していきます。
時代が流れ、そして現在、空手発祥の地・沖縄で最も大きく栄えた「沖縄4大流派」
と言われるのが小林流、松林流、上地流、剛柔流となりました。
それぞれ「首里手」「那覇手」「泊手」の流れを汲んだ流派です。

④本土に渡り流派乱立 競技色も強くなる
沖縄から本土に空手を伝える時、競技要素を取り入れた結果様々な流派が乱立します。
寸止めで当てない流派、防具をつけて当てる流派、防具をつけず当てる流派
(フルコンタクト空手)等々。
中には形を行わず組手のみを行う流派等もあり、空手といっても様々に分かれ
まさに玉石混交の様相を呈しています。

しかしながらあまりに競技化・スポーツ化へと舵を切った空手に疑問を持ち、
「本来の空手を学びたい」といった原点回帰の流れが出てきています。




「空手」というものを想像した時、そこには人それぞれのイメージがあると思います。
ですが元々の空手(手)が生まれた当時の特徴は、今の空手からは想像が難しい特徴がいくつかあります。
①空手は武術=素手で人を殺す技。競技など存在し得ない。
武術として生まれた空手は当然ながら真剣勝負の世界。競技要素など本来皆無でした。
しかし本土へ普及させる際、競技要素を取り入れ、現在では逆に競技を行わない流派の方が
見つけることが難しい状態となってしまいました。競技に否定的な意見はありませんが、
空手の源流を学ぶのに競技要素は廃していくというのが私たちの方向性です。
②師と弟子はマンツーマン指導。そして他言無用。
言っても空手=殺人術 を教わってる訳です。なので基本的に師が弟子をたくさん集めて稽古する
のではなくマンツーマン指導を行い、弟子同士も横のつながりなど持たず誰が誰に空手を教わって
いるのか知らない状態でした。しかも現代のように空手を習っているなんて気軽に言えない時代。
他人には秘密にしていたというのが昔の空手です。
③その仮想敵は「薩摩示現流」剣士。
琉球士族において研究され練られた「手(ティー)」
中でも首里手及び泊手に関してはその仮想敵はその当時薩摩藩士に隆盛をきわめた「示現流剣士」
刀を構えた剣士の懐に一瞬にして入り込み、素手で相手を制する武術。それがスピードを命とする首里手・
泊手の極意です。だから「二の手」「三の手」はありません。一撃で相手を仕留めなければそれは自分が次の瞬間
切られることを意味するからです。
④攻撃と防御は同時でなければならない。
「防御(受け)を行ってから攻撃を仕掛ける」「攻撃をしてから防御する」のでは遅い。
なぜなら相手は剣士であり一瞬の隙に切られて死ぬからです。
攻撃をするということはつまり相手の間合いに入ること。
間合いに入った瞬間に相手を制するには防御と攻撃の間が(出来る限り)開かないことが理想。
なので沖縄空手には「夫婦手(メオトゥディー)」という両方の手を同時に使うといった技が
多数あるのです。
⑤「触・即・技(しょくそくぎ)」を体得せよ。
沖縄空手の真髄である「触・即・技(しょくそくぎ)」。
攻撃した側が相手に技を受けられた時、その手足が痛くて(破壊されて)使えないほどのダメージ
を与えており、次の攻撃を繰り出させないほどに戦意喪失をさせたり。
それこそが攻撃と防御を可能にする技。
(相手に)触れたら、それ即(すなわ)ち技である。”相手の手足を剣と思え”という所以です。

以前より琉球(沖縄)には「手(ティ)」と呼ばれる武術がありました。
1429年に琉球(沖縄)が尚巴志(しょうはし)により統一され武器を禁じられると
素手の武術である手(ティ)や、農機具等を使った武術が発展します。
その後琉球は、ジャワ・スマトラ・タイや中国等の南国諸国との交流が盛んになり、
同時に各国の武術の要素を吸収、改革され「手」が発展していきます。

②発展した「手」は3つに分かれる
「手」が発展すると、琉球各地に広がりそれぞれの地名をとって
首里手(しゅりて) 那覇手(なはて) 泊手(とまりて)
と呼ばれ始め、それぞれ特徴を持ち始めます。
首里手:関節・スピード(素早さ)を重視 自然な呼吸法
那覇手:筋肉・パワー重視 意識した呼吸法
泊手 :首里手に非常に近いがさらに関節躍動を使った技が多い

③「沖縄4大流派」が起きる
3つの「手」の中心人物や、その弟子たちがやがて様々な流派を興していきます。
時代が流れ、そして現在、空手発祥の地・沖縄で最も大きく栄えた「沖縄4大流派」
と言われるのが小林流、松林流、上地流、剛柔流となりました。
それぞれ「首里手」「那覇手」「泊手」の流れを汲んだ流派です。

④本土に渡り流派乱立 競技色も強くなる
沖縄から本土に空手を伝える時、競技要素を取り入れた結果様々な流派が乱立します。
寸止めで当てない流派、防具をつけて当てる流派、防具をつけず当てる流派
(フルコンタクト空手)等々。
中には形を行わず組手のみを行う流派等もあり、空手といっても様々に分かれ
まさに玉石混交の様相を呈しています。

しかしながらあまりに競技化・スポーツ化へと舵を切った空手に疑問を持ち、
「本来の空手を学びたい」といった原点回帰の流れが出てきています。
<沖縄空手系統図(首里手・泊手・那覇手)>
(引用:沖縄伝統空手道HP)




「空手」というものを想像した時、そこには人それぞれのイメージがあると思います。
ですが元々の空手(手)が生まれた当時の特徴は、今の空手からは想像が難しい特徴がいくつかあります。
①空手は武術=素手で人を殺す技。競技など存在し得ない。
武術として生まれた空手は当然ながら真剣勝負の世界。競技要素など本来皆無でした。
しかし本土へ普及させる際、競技要素を取り入れ、現在では逆に競技を行わない流派の方が
見つけることが難しい状態となってしまいました。競技に否定的な意見はありませんが、
空手の源流を学ぶのに競技要素は廃していくというのが私たちの方向性です。
②師と弟子はマンツーマン指導。そして他言無用。
言っても空手=殺人術 を教わってる訳です。なので基本的に師が弟子をたくさん集めて稽古する
のではなくマンツーマン指導を行い、弟子同士も横のつながりなど持たず誰が誰に空手を教わって
いるのか知らない状態でした。しかも現代のように空手を習っているなんて気軽に言えない時代。
他人には秘密にしていたというのが昔の空手です。
③その仮想敵は「薩摩示現流」剣士。
琉球士族において研究され練られた「手(ティー)」
中でも首里手及び泊手に関してはその仮想敵はその当時薩摩藩士に隆盛をきわめた「示現流剣士」
刀を構えた剣士の懐に一瞬にして入り込み、素手で相手を制する武術。それがスピードを命とする首里手・
泊手の極意です。だから「二の手」「三の手」はありません。一撃で相手を仕留めなければそれは自分が次の瞬間
切られることを意味するからです。
④攻撃と防御は同時でなければならない。
「防御(受け)を行ってから攻撃を仕掛ける」「攻撃をしてから防御する」のでは遅い。
なぜなら相手は剣士であり一瞬の隙に切られて死ぬからです。
攻撃をするということはつまり相手の間合いに入ること。
間合いに入った瞬間に相手を制するには防御と攻撃の間が(出来る限り)開かないことが理想。
なので沖縄空手には「夫婦手(メオトゥディー)」という両方の手を同時に使うといった技が
多数あるのです。
⑤「触・即・技(しょくそくぎ)」を体得せよ。
沖縄空手の真髄である「触・即・技(しょくそくぎ)」。
攻撃した側が相手に技を受けられた時、その手足が痛くて(破壊されて)使えないほどのダメージ
を与えており、次の攻撃を繰り出させないほどに戦意喪失をさせたり。
それこそが攻撃と防御を可能にする技。
(相手に)触れたら、それ即(すなわ)ち技である。”相手の手足を剣と思え”という所以です。

Posted by シュリ at 22:49│Comments(0)
│道場について